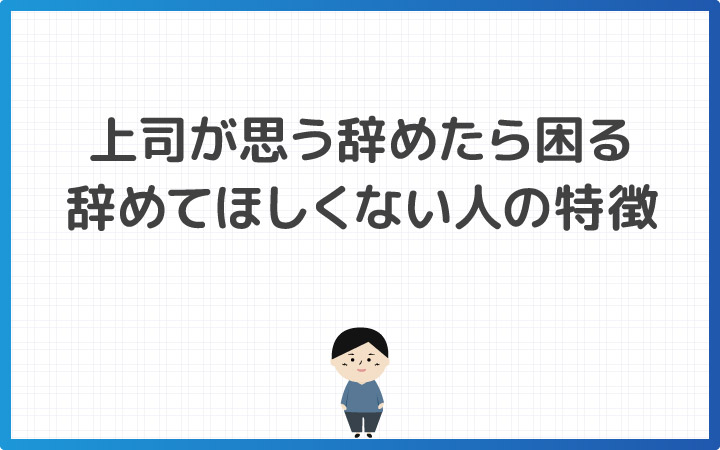
上司・先輩もいい人だけど、最近ミスしてばかり…。
いつも許してもらえるけど、本当は「使えないな」とか思われていそうで不安になる。
かといって辞めたくないので何とかしたい…そんな時に知っておきたいのが、上司が辞めたら困る・辞めてほしくないと思っている人の特徴です。
上司・先輩が何を求めているのか、それが分かると会社で求められる人になれます。著者:osugi
辞められたら困る人の特徴とは?
入った会社で、楽しそうに働ける人もいれば、社内トラブルなどによって退職を選んでしまう方もいますよね。
辞めるキッカケとしては、上司に毎回怒られたり、仕事がうまくいかなかったり、ネガティブな出来事が多い。
逆に続いている人は、社内で自分の居場所を見つけたり、求められる人材になっているからこそ、辞めることを考える暇さえないくらい、毎日が充実している。
この違いは、上司・先輩・同僚・後輩にとって”辞められたら困る人”になっているからです。
では、辞められたら困るとは、どんな方を指すのか特徴をまとめてみました。
1. 大小問わず成果を出している
「成果」と書きましたが、ここの解釈には気を付けないといけません。
仕事上の成果とは、よく売上や目標達成に対して使われますが、確かにそれはありつつも、日ごろの成果がすごく大事。
たとえば、誰か困った人がいた時に、すかさずサポートしてあげたり、定期的な作業の声がけをしたりと、成果=行動を見せる。
上司としては、指示待ちで動かない方よりも、率先して自ら考え行動してくれる方を好ましいと思う傾向があります。
2. 他がいやがる仕事を率先して対応してくれている
業務の中には、あなたがしたい仕事もあれば、やりたくない仕事だってもちろんあると思います。
選り好みをして、好きな仕事ばかりを対応していると、上司からは「扱いずらい社員だ」と思われてしまう場合も。
やりたくない仕事はもちろん、あえて手間のかかる仕事を引き受けたり、社内を円滑に回してくれる方を好ましいと思う傾向があります。
3. 上司の発言にフィードバックをしてくれている
上司は普段から、メンバーのためだったり、あなた自身のために色々話を聞き、時にはアドバイスなどもありますよね。
そういった時に、上司から受けた情報に対して、何かしらフィードバック・アクションをしてあげる。
たとえば、良さそうなセミナーを教えてくれたら「気になってたので行ってみます!」と伝えたり、アドバイスをもらった時には「そういう視点で考えられていませんでした、次からは注意できそうです。」など。
上司からの情報共有によって、あなたや仕事が良くなっていくことが示せるフィードバックが行えると「伝えて良かったな」と上司も思ってくれて、そこからさらに信頼関係が深まっていきます。
4. きちんと表情を見せている
あまり意識してない方も多いですが、上司はあなたの表情・発言の細かい部分まで気にしています。
「なんか暗い顔してるな」「最近ネガティブな発言が多くなってきたな」と、同じチームのメンバーとして、あなたのことを意識している。
もし、気持ちが落ちてたりモチベーションが低くなっていたり、そんな時は無理して明るい顔をする必要はありませんが、元気な時はきちんと元気な様子を見せてあげるんです。
表情はその方の内面を表すバロメーターでもあるので、普段から何考えているか分からない、表情からも読み取れない人は付き合いづらいと感じますが、その逆であれば上司自身が「理解できる相手だ」と思い、手放したくないとも思ってもらえる。
5. 言葉の表現に配慮がある
今は働き方が変わって、出社もあれば在宅のテレワーク(リモートワーク)で仕事をする機会も多くなりました。
そのため、チャット・メールなどのテキストコミュニケーションがさらに増えている。
たとえば丁寧な言葉は、ビジネス上もちろん大事な要素の一つであるものの、丁寧すぎると心の壁を感じやすかったり、いらぬ誤解や誤解釈をされてしまいトラブルになることも。
テキスト上のコミュニケーションに配慮があり、連絡をとっていて気持ちいいやり取りができる人とは、もっと話したい、または話してても苦にならないので令和時代では重宝されます。
上司はもちろん、周りのメンバーも同じく、話しやすい人は辞めては困る存在に。
6. 自分の成果をひけらかさない
仕事で成果を出して「すごいでしょ!」と、毎回自慢やアピールをしてくる人はいますが、かなりきわどい存在。
成果としてアピールしたいのは、上司も「頑張ったのだからアピールしたいよね」と一定の理解はしつつも、そのことで周りを萎えさせているのであれば違う話。
伝え方に配慮があり、自分ではなく関わってくれた・サポートしてくれた方も一緒にアピールしてくれるのであれば、周りを鼓舞してくれる存在として、上司としては頼れる存在になります。
7. 否定から入らない
仕事の中では、必然的に上司・部下で上下関係が作られてしまいやすい。
そうなると、信頼関係が築けていない場合は部下からの反発、上司からの発言に対する否定的な発言が多くなってくることがあります。
否定をしてはいけない、という話ではなく、否定はさらに信頼関係を壊すだけであることを理解しておきたいところ。
否定ではなく、違う視点で考えたらこういうのものありますよね?など、代替え案などを提示しながら、モノゴトをさらに良くしていく方向へ進めてくれる存在は、上司として頼りがいがある存在に変わります。
8. 指示内容に対する理解度を高める
仕事上で行われる上司からの指示、意外と抜け漏れがあったり、背景を伝えずに「なぜやるのか」が分からないことも多いですよね。
そのまま進めてしまうと、結局上司が望んでいた内容ではなく、やり直しや怒られることもある。
言われたことに対して、何度も聞いたり質問するのは、部下からしてみれば怖い行動ですが、間違えた・理解できてない指示のまま進んでしまった方が困ってしまう。
上司としても、どのような伝え方であれば伝わるのか分かっていないことも多いため、あなたの視点から理解するための質問・疑問を投げかけて、理解に努めてくれる部下とはずっと一緒に仕事をしていきたいと思うものです。
9. 弱音を聞いてくれる
あなたの上司も、上司だからこそ悩みの一つや二つあると思います。
しかし「上司だから」とか「部下に弱気を見せてはいけない」と常に気を張っている上司もいる。
そうなると心に余裕がなくなって、指示が雑になったり成果を急いだりして、困るのはあなたの方になってしまいます。
一つ試してほしいのが、上司の弱音を引き出すこと。
弱音=内面を出せる存在としてあなたが認識されれば、上司にとっては替えのきかない唯一無二の存在に。
10. 連絡を比較的すぐ返してくれる
仕事を段取りよく、スムーズに進めるには、関わる人同士のコミュニケーションレベルが問われてきます。
たとえば確認連絡をして、それを待たないと進めない時など、連絡が返ってこなければ何も進められなくなる。
よくあるのが、上司からの連絡が遅くて進められない、というものですが、その逆で部下からの連絡が遅くて上司のスケジュールが遅くなることもあります。
上司としては、返事・回答を早くもらえることで次に動けるので、連絡が早い人には信頼を感じて辞めてほしくないと思われる。
質問されたことにすぐ回答ができない場合などは、なぜ回答がすぐ出せないのか、どのくらいなら出せるのかなど、事前の連絡をしてあげるだけでも印象がだいぶ変わってきます。
11. トラブルになる前に相談/確認/連絡してくれる
上司にとって困ることのTOP10に入るのが、部下から大きなトラブルになってからの報告です。
本当なら、もっと手前で解決できていたものを、おおごとになってから教えられても困るだけ。
トラブルになりそうな状況など、火が燃え始めたタイミングで共有することで、的確なアドバイスによってすぐに鎮静化もできる。
トラブルになってからだと、その後の処理で時間を余計に使ってしまうので、いつも相談・確認・連絡が早い部下には信頼を感じて、辞めたら困る存在として認識してもらえます。
12. 1を伝えれば10行動してくれる
あなたも聞いたことがあるかもしれませんが、1伝えて10行動してくれる人が求められる、という話。
これは、1伝えればモノゴトの理解を発展させて、求めていた以上の行動を起こしてほしいという上司側からの期待を表す表現ですが、実際はそんな簡単ではありません。
そもそも分からないことだからこそ聞いたのに、そこから思考を発展させて、情報をたぐり寄せ…求めた以上をするのはハードルが高い。
そこまでは無理だとしても、自分で考えて行動に起こしてくれる人は、上司からの信頼を得やすく、替えのきかない存在にもなります。
13. 他社員の模範になってくれる
会社に入れば、会社として掲げている行動規範や目標などがありますよね。
その行動に沿う方が評価されていく仕組みでもある。
つまり行動規範に沿って、動いてくれる存在を求めており、そのような存在になれれば上司としても評価しやすい。
他社員の模範になってくれるような存在は、会社が求める人材であり、それは上司が辞めてほしくないと思う人材でもあります。
14. 依頼した内容はすぐ行動してくれる
仕事のスピードは、そのまま上司の評価に還元されます。
言ったこと、お願いしたことを、即動いてくれる人は、上司からの信頼を毎日のように積み重ねていけて、欠かせない存在となります。
15. 自分の考えを伝えてくれる
すべて何か言われた通りに動く人よりも、どう思っているのか・考えているのか、意見をハッキリと伝えてくれる人は、コミュニケーションが取りやすいと感じます。
注意点は、考えなどを伝える時、否定ではなく、なるべくポジティブな形で伝えること。
否定をすれば、上司自身が否定されていると認識させる場合もあり、信頼は落ちやすい。
16. 指示待ちではなく先に聞いてくれる
何事も、言われてから動くのではなく、先に何をすればいいか聞いてから、動くのがお勧めです。
役職者は特に、指示待ち人間を嫌い傾向がある。
自ら動いて失敗するのが怖い場合は、先に「こういったことは必要ですか?」と、先に聞くことで気が利く存在として、上司から信頼が厚くなっていく。
17. 遅刻欠席が少ない
遅刻や欠席など、状況によってはどうしても発生してしまうものですが、それでも基本スケジュール通りに動いてくれる人は、信頼されやすい傾向です。
それは、スケジュールを崩さない人は、上司としても計算しやすく、組織運営・チーム体制を作るのに楽をできるから。
動きが不規則な人ほど管理がしづらいので、嫌われる可能性は高くなります。
18. 他の人の前で上司を評価してくれる
あまり上司自身を褒める機会はないかもしれませんが、意外と褒められるのが好きな上司はたくさんいます。(人間ですから)
一般的には、上司が部下を褒める流れですが、部下から上司を褒めてあげる。
無理して褒める必要はなく、むしろ嘘やゴマすりだと捉えられるかもしれません。
自然に、本当にすごい・感謝している、そのような気持ちが出たら、言葉にしてあげるだけでも喜ばれ、一緒に働きたいと感じてもらいやすくなります。
19. 困ったときはすぐに声をかけてくれる
上司だからと言って、すべてを完璧にこなせるわけではなくミスは出てしまうものです。
仕事量も多岐にわたるためキャパオーバーになりやすく、弱みを見せられないからこそ、自分だけで頑張ってしまう。
そんな事が続けば、上司に話しかけても返事がもらえず、質問したいのに聞けないなど、コミュニケーションが滞ります。
あなた自身に余裕がある時でいいですが、上司が困っていそうならすぐ声をかけて、サポートを申し出てあげると、感謝によってあなたが欠かせない存在となっていきます。
20. 淡々と業務をこなしてくれる
やるべき仕事をこなすのは、当たり前のようで当たり前ではなく、何か一つ欠け間違えるだけで進まなくなります。
それでも、毎日スケジュール通りに一定の質を保ちながら、淡々と業務をこなしてくれる人は大変重宝します。
進まない仕事より、進む仕事をする人の方が好まれるため、別に大きな成果をあげずとも、やるべきことに集中して淡々とこなせる人は上司からの評価は高くなる。
21. 上司が陰ならサポートしてくれたことに感謝を伝える
最近、上司に感謝を伝えていますか?
たぶん、何かを聞いて返答もらえた時に「ありがとうございます」など、日常的な会話の中で、感謝を述べることはありますが、それらは感謝であって感謝ではない。
もっと他に、上司が特別してくれたことや、陰ながらサポートしてくれたことに気づき、そこに対して感謝を伝える。
つまり、上司のことを見ているからこそできる感謝を伝えるということです。
22. 上司自身の雑務を引き受けてくれる
上司の仕事は、役職によって権限が増えるからこそ、難易度の高い業務が入りやすくなっています。
当然、使える時間には限りが出てくるため、その中でどうするかやりくりする。
しかし、そもそも減った時間の中でやりくりするのは難しく、残業や休日中などを利用して、業務をしているのが正直なところ。
無理をしていそうな上司には、あなた自身で何か雑務など巻き取れそうな仕事があれば、率先して巻き取ってあげましょう。
助けてくれる部下がいれば信頼が高まり、欠かせないパートナーとして認識されるようになります。
最後に。
上司が思う辞めたら困る・辞めてほしくない人の特徴をまとめていきましたが、もっと簡単に言えば上司と信頼関係が築ける人。
全ては信頼関係の程度によって、辞めても困らない人か、辞めたら困る人、どちらの認識を持たれるのか変わってくる。
もっと欲を言えば、上司の心の支えになってくれる人。
部下としては逆にサポートしてもらいたいですが、上司は上司で板挟みになったり成果を上から求められ疲弊していることも多くて、上司自身も困っています。
だからこそ、信頼関係を築ける存在だと知ってもらえることで、上司から求められる存在になれます。