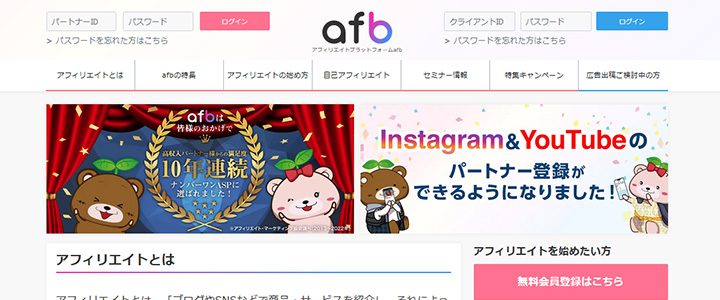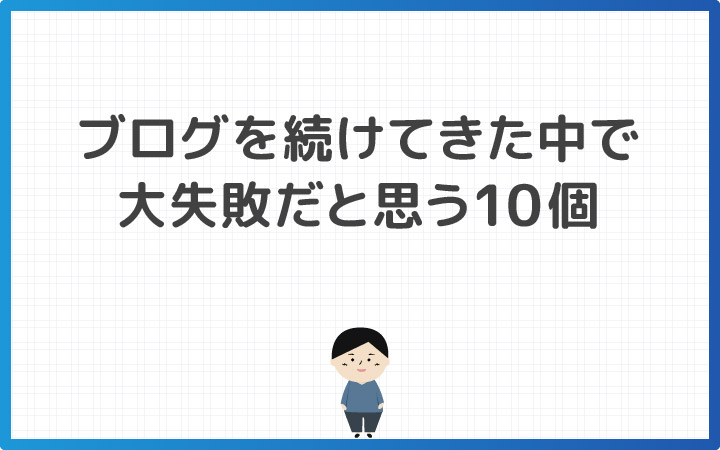
学生のころから国語も苦手、長文も書けなかった、そんな状況で大人になったぼくは、仕事でも「長い文章」を使ったのはせいぜいメールくらい。
ブログを書くなんて思いもしませんでした。
しかし、会社の業務の一環で、ブログの運営に携わってきてから7年以上経ち、今では日常的に文章を書くことが仕事の基本になっています。
当然最初からうまく進めてこれたわけではなく、書いた記事が1年以上もまったくアクセスが増えない記事があったり、誤字脱字も多い(今もですが)、そんな中でも失敗のおかげで「悪いやり方」に気づいて、ブログを伸ばす”すべ”を身につけられました。
ぼくがこれまで書いてきた記事、またはブログ運営(メディア)で大失敗した10のことから、どんな学びが得られたのかまとめています。
成功も失敗も、どちらもよい経験であり、身銭を切った分使えるノウハウが手に入ります。この情報が、あなたのブログライフのお役に立てられればうれしいです。著者:osugi(@osuuuugi)
- 目次
- 1. 書けば「見てもらえる」と甘い期待をしていた
- 2. 「このくらいでいいかな」と自ら妥協記事を書いてしまっていた
- 3. 長文さえ書ければアクセスが増えると思っていた
- 4. 記事を増やせば評価が高まるため本質を見失っていた
- 5. 無理して記事を書き続けてしまった
- 6. 「稼げる」と聞いた興味の無いテーマを選んでしまっていた
- 7. 検索順位の1位になった記事をそのまま放置してしまった
- 8. 伸びていると油断して記事を書かなくなってしまった
- 9. 結果が悪いことを他人のせいにしてしまった
- 10. 絞り込み検索機能の検索結果をすべてindexさせてしまった
- 最後に。
1. 書けば「見てもらえる」と甘い期待をしていた
仕事でブログに携わった当初、そもそも長文を苦手としていたので、長い文章を書くことが一番の問題ポイントでした。
普段からメールやチャットを使って、文章には慣れていたものの、何をどう書けばいいかすら分からない状態だったので、全部が見様見真似で進めていた。
しかし、ブログで一番たいへんなことは長い文章を書くことだと思い込んでいたぼくは、文章さえ書ければ「まぁ見てもらえるだろう」と甘い期待をしていたんです。
結果、書く記事書く記事ぜんぶが、まったく見てもらえない…。
ブログの世界を簡単に見すぎていたことが原因です。
ぼくなんかが書いているなら、回りにはすでにブログを何記事も書いている、ずっと昔から続けている、情熱をかけて文章を書いている、こんな人達がいて、回りを見ようともせず、自分だけが文章を書いている気になっていたのかもしれません。
ブログ初めは、周りの状況が全然見えていませんでしたが、やればやるほど現実を目の辺りにして、壁の高さも感じて打ちひしがれていた記憶があります。
仕事の一環で携わり始めたブログでしたが、完全になめてかかっていたので猛反省。
2. 「このくらいでいいかな」と自ら妥協記事を書いてしまっていた
最初記事を書いていたときは、どこまで書けばいいのかな?と、程度が分かっていませんでした。
しかし、週に2~3記事書き、それが1年2年と続いたあたりから、どのぐらい書けば十分かな?といった自分なりの基準が勝手に出来上がっていた。
「ここまで書けば十分だろう」と勝手に、ユーザーさんが求めている範囲を決めてしまい、品質を高める思考を捨てて、工場生産するような感情で書いていたんです。
そんな思考・感情のまま書いた記事は、当然ユーザーさんに満足してもらえない不十分な記事が量産されてしまって、結果としてアクセスの伸びが止まってしまった。
自分で限界や品質向上への意識を閉ざして、誰も得しないような記事を書き続けていた時期があります。
これは「書き慣れた」&「アクセスが上がっていた」ことが原因であり、いつの間にかブログ記事を書くための情熱をセーブしていたからだと思います。
自分の「このくらいでいいか」と思う気持ちは、成長を止める元凶でしかないので、常に上を目指し続ける気持ちが大切。
3. 長文さえ書ければアクセスが増えると思っていた
アクセスを増やすために、さまざまな記事や情報をむさぼり読んでいると「品質」という共通ワードをよく見かけるようになりました。
ブログの品質?記事の品質?あまり具体的なことが書かれている情報はありませんでしたが、要はたくさんの情報が入っていればいい、そう解釈。
そのため、とにかく長文が書ければ、アクセスが増えると思い込んで、せっせと長文ばかりを書くようになっていました。
これは書いていくうちに気付いたことですが、結果として長過ぎる文章は「読みづらい」だけならいいですが、ユーザーさんにとっては情報を探しづらいだけ。
自分の立場で考えると、1記事に3万字や5万字もあったら、A4原稿用紙で言えば75~125枚分にもなって、小説やビジネス書を読むぐらいになってしまうので、読んでいる時間もない。
インターネット検索をしている方の多くは、今すぐに不安を解消したいので、ダラダラと時間をかけてまで情報を得ようとはせず、パッと見れて、スッと理解できる情報を求めている。
長文にすれば、たくさんの情報を入れ込めますが、ユーザーさんが求めていない場合もあります。
完全に自分都合の文章を書いていたことに気づき、必要量を考えながら文章を書くようになりました。
4. 記事を増やせば評価が高まるため本質を見失っていた
業務として行っていたブログ、会社へ報告するときには必ず「数字」が必要でした。
今週は何記事書いたの?今期は合計何記事書いたの?と。
数値が多ければ多いほど、自分自身の評価に繋がってくるため、記事一つ一つの品質ではなく、どれだけたくさん書いたかに意識が向けられていた。
その意識を前提として、記事を増やせば増やすほどアクセスも上がると勝手に思い込んでいたので、会社の目標と記事数が連動して、記事数を増やすことばかりを行っていた時期があります。
しかし、ユーザーさんが求めていないような記事を量産してもアクセスは増えるはずもなく、頑張りと結果が連動しないことも多かったです。
5. 無理して記事を書き続けてしまった
文章を書くとは、単純そうで実はとても繊細なもの。
文章は今まで生きてきた中で得られた知識(覚えてきた単語・意味など)をもとに生み出されるだけでなく、書くときの感情で生み出される文章が大きく変わってきます。
たとえば、何か悲しいことがあったときに文章を書き出そうとすれば、マイナス感情に支配されているためか、ネガティブな言葉が出てきやすくなる。
その逆で、心が健全でポジティブな状態であれば、その感情に引っ張られてユーザーさんが喜んでくれるような言葉が出てきやすい。
文章と心は密接に繋がっているため、無理して記事を書くのはよくない。
そのことに気づかず、無理して毎日毎日記事を書き続けてしまい、あまり結果が振るわない記事が多くなってしまった時期があります。
6. 「稼げる」と聞いた興味の無いテーマを選んでしまっていた
あまり自分のブログの結果が良くないと、どうしても他ブログと比較をしてしまう。
その中で、うまくいっている、または稼げているブログの存在を知ると、自分がそのテーマに興味がない、または知見を持っていなくても「あの人が稼げているなら自分も行けるんじゃないか?」と浅はかな気持ちで手を出してしまったことも多い…。
しかし、専門的な知識がない、興味がない、情熱をかけて書けないテーマでいくらブログを書いても、そこには薄っぺらい情報だけがあるだけで、アクセスは一向に増えませんでした。
こんなにも世の中に情報が溢れている状態なのに、薄い情報しか載っていないブログは価値を発揮できず、その結果としてGoogleさんなども検索上位へは表示してくれません。
また、他人の状況と自分の状況はまったく異なり、同じことをしても状況が変われば再現することは難しい。
そのことに気づかず、何度も失敗してきました。
自分が最も力を発揮できるテーマでブログを書くことが、一番成功に近づくということに改めて気づいた失敗です。
7. 検索順位の1位になった記事をそのまま放置してしまった
ブログを書いていると、どんどん書きたいことが見つかり、新しい記事を書き続けてしまいます。
この状況はむしろ良いことですが、今まで書いてきた記事は当然、自分だけが書いているテーマではなく、他ブロガーさんや法人含めて、たくさんの人が書いている。
そんな中、ずっと古い情報を載せ続けている記事は、他のもっと良い記事にすぐ評価を追い抜かれてしまって、アクセスが徐々に減っていきます。
今1位だったとしても、ずっと1位になれるかは違う話であり、今1位だからと完全に油断していたため、いつの間にか他記事に順位を追い越されてしまっていた。
負けを取り戻そうとして記事を改修しても、すぐに結果が出るわけではないので、1位だった記事でアクセス数を稼いでいたぼくのブログは、大きく後退してしまったことがあります。
永遠の1位なんて存在せず、むしろみんなが1位を獲りにきている状況の中、少しも気を抜けないのがブログ。
品質を高め続ける意識が抜けてしまうと、あっという間に転落する体験をしました。
8. 伸びていると油断して記事を書かなくなってしまった
記事を書き、ブログ全体のアクセス数が増えていくと「慢心」が生まれやすい。(ぼくだけじゃないかもしれませんが…)
ブログの基本は、前に書いた記事が評価されて、アクセスが高まっていく。
つまり、頑張った過去が今になって「成果」として現れているということ。
この原理原則を忘れ「今」だけを意識してしまうことで、慢心が生まれます。
今を頑張らなければ当然「過去」は作れず、過去を作れたとしても質の低い過去になってしまっては、アクセスは増えていきません。
それにライバルや競合は、黙々と質の高いブログを書き続けているのに、自分だけが止まっていては追い抜かれてもしかたありませんよね。
こんな単純なことに気づかず、ブログを書く手をゆるめてしまったがために、アクセスが伸びなくなり、あたふたした経験を何度もしてきました。
9. 結果が悪いことを他人のせいにしてしまった
これは業務で携わっていたときのブログの失敗ですが、複数人で運営していたことで、他責の心が生まれてしまい、結果がでないことを自分以外のせいにしてしまったことがあります。
直接は言わないものの「自分はこんなに書いているのに、書いてないあの人のせいだ。」と思ってしまい、なにもわるくない同僚に対して八つ当たりをしてしまったことも。
ブログの結果がふるわないとき、さまざまな原因が潜んでいるため、当然誰か一人のせいなんかではありません。
しかし、その時は自分のプライドが許せなかったのか、他人のせいにして気持ちを軽くしたかったのか、他責で逃れようとしてしまった。
本来であればチームで協力して乗り越えていく状況なのに、自分が「一番正しい」という思考で凝り固まってしまい、いらぬ衝突を生んでしまった経験があります。
まず誰かのせいにするのではなく、そんなマイナス思考ではなくて、今後どうすればいいのか?プラス思考で進めていくべき状況でした。
10. 絞り込み検索機能の検索結果をすべてindexさせてしまった
ブログを書いてきた中で、一番の大失敗と言えるのが、無駄なページをGoogleなどにindexさせてしまったこと。
少し昔なので、正しい数値は分からないのですが、9,000件ほどの無駄indexをさせてしまい、ブログ自体の評価が大きく下がって仕事に影響を与えてしまったことがあります。
その時は毎日数百件のindex削除申請を行ったり、無駄なindexページを登録させないようにブログの構造から見直したりと、毎日気が気でない状況が続いていました。
原因としては、絞り込み検索を実装した時に、絞り込み検索結果のページがそのままindexされる仕様にしてしまっていたので、絞り込み項目とその掛け合わせにより、数千件の無駄indexを生んでしまった…。
一番の大失敗であり、売上も下がってしまったことで大反省の出来事です。
最後に。
ブログを書き続けて大失敗した経験をまとめてみました。
結果として、ぜんぶが自分の中では大失敗でありましたが、この大失敗によってブログへの向き合い方が大きく変化。
仕事だけだったのが、このブログのようにプライベートでも始めるようになりました。
大失敗と書きはしましたが、失敗はすべて成功へと続く過程でしかないため、今のぼくがブログを楽しむうえで欠かせない経験だったと思っています。著者:osugi(@osuuuugi)