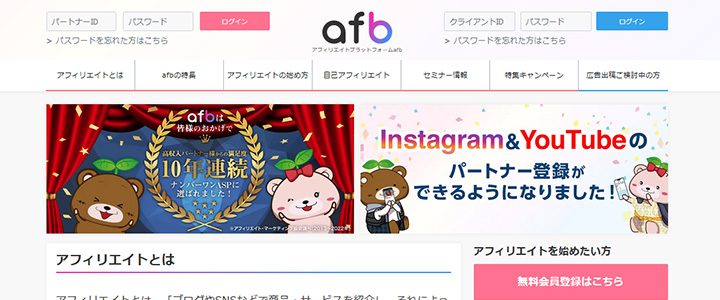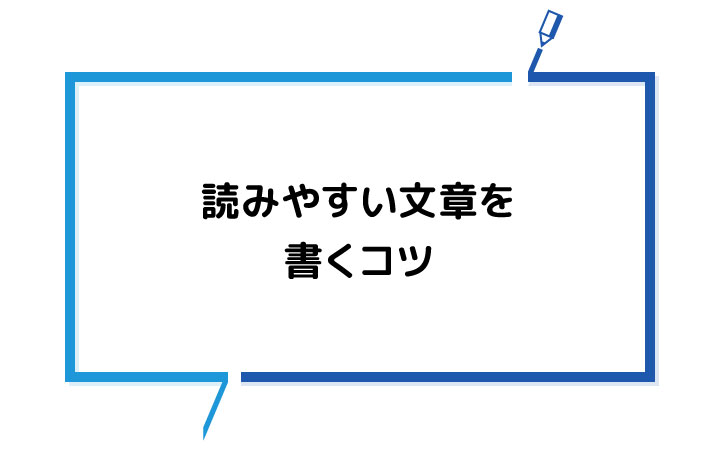
ブログ(webサイトを含む)を運営するのであれば、文章との戦いの連続だと思います。
読みづらければアクセスが減り、読みやすければアクセスが増える、シンプルな世界。
文章一つで、大きくビジネスが変わるシーンだってある。
そんな文章を書くコツを私と一緒に見ていければ嬉しいです。
すぐにコツから見たい場合は読みやすい文章を書く5つのコツから見てもらえればと思います。
なぜ読みやすい文章を求めるの?
あなたが読みやすい文章を求めているのは、どんな理由からですか?
- SEOを強くしたい
- ファンを増やしたい
- アクセスを増やしたい
このように、本当に求めているのは、読みやすさを活かした、目的達成の方法になってくるのではないかなと思っています。
その場合は、ただ単純に読みやすい文章を書けるだけでは足りず、もっと奥に踏み込んだ内容が必要になってくる。
読みやすい文章を書いて→読んでもらって→アクセスを増やして→ユーザーさんにファンになってもらい→何回もブログに来てもらいたい。
読みやすい文章は、目標達成のための過程の1つでしかありません。
この図式のような良い流れを作るには、最終的な目的達成を意識して、文章の読みやすさを知る必要がある。
「目的達成のため?そんなの分かってるから!」と、お怒りを頂くかもしれませんが、大事な事だと思ったので、読みやすさを知る前に、改めて見て頂きました。
そもそも、なぜ読みやすい文章にする必要がある?
読みやすさがなければ、一体どうなるのか。
例えば、
- マニュアル
- 仕様書
このような媒体で使われる文章は、堅苦しく、難しい言葉ばかりで、正直読む気にもなれませんよね。
さらに、文章だけ長くて、分厚くまとめてある…。
こんなの誰が読むの?と思うことがほとんど。
もし、マニュアルや仕様書に書かれているような文章でブログが書かれていれば、誰が読みたいと思うのか。
ほんっとーーーーーの物好きじゃなければ、そんな文章が書いてあったら、スマホであればスワイプですぐに消され、PCだったらタブごと消されてしまう。
そのため、読みやすさとは、自分の文章を読んでもらうための、最低限の礼儀?に該当するんじゃないかなと思っています。
数ある記事の中から、自分の記事を選んでくれて、しかも毎日忙しくて時間がないのに、わざわざ時間をとって読んでくれる。
ユーザーさんには、見てくれるお礼として、最低限の読みやすさは、なければいけない。
読みやすさの意識がない場合は、「私を見て!俺を見て!」と自分の事ばかり意識して、読んてくれるユーザーさんへの意識が薄れている証拠かもしれません。
読みやすい文章にしようとしている=ユーザーさんを意識している。
単純な読みやすさを学べばいいのか、という事ではなく、ユーザーさんを意識できているか?ここがとっても大事なんだと思いました。
その上で、読みやすさを覚えていくと、素敵な文章がどんどんできるようになるんだと思います。
ユーザーさんの事を考えた文章の読みやすさ、その先のファンになってもらえる思考で文章が書けるようになるコツを、私と一緒に見ていければと思います。
私が書く読みやすさが正しいのか?と言われれば「絶対にそうです!」とは言えないですが、私自身が感じた・学んだ事からの読みやすい文章を書くコツなので、その点をご理解いただき、見て頂くといいかもしれません。
数あるうちの1つの考え方として、見ていただければ嬉しいです。
読みやすさは読み手との関係値が低い時こそ効果を発揮
あなたの文章を見てくれる、読み手の状況によっても、読みやすさが大きく影響します。
▼書き手と読み手の関係値が低い
- 文章を読みたいわけじゃなく情報を知りたいだけ
- 欲しい情報だけすぐに欲しい
関係値が低い場合は、かなりドライな関係…。
もし、関係値が低い状態で、読みづらい文章を書いてしまった場合、すぐに別の記事へ移動されてしまう。
そのため、書き手と読み手の関係値が低い時ほど、読みやすい文章が求められてきます。
▼書き手と読み手の関係値が高い
- 書き手の文章が好きだから見たい
- 他の文章(記事)も見たい
関係値が高い場合は、どんどん親密に。
情報を知る為だけに見てもらっていたものが、次も見たい・もっと見たいへ変換していくのも、読みやすい文章が影響します。
読みやすい文章を書くことで、たくさんのメリットが得られるため、あなたにも読みやすい文章を書くコツを覚えてもらえると嬉しいです。
読みやすい文章を書く5つのコツ
私がお伝えできる読みやすい文章を書くコツは、ブログなどwebメディアを対象とした書き方となっています。
そのため、以下の条件を確認頂いた上で、内容を見てもらうのがいいかもしれません…。
活用できるシーン
・会社の公式サイト
・ブログなどのwebメディア
活用できないシーン
・小説
・論文
・書籍
堅苦しい文章を書く媒体には不向きなので、それ以外の場合に活用できます。
内容としては、
- 読みやすい文章を書くコツ5つのポイント
- 1. 文章を書く意識
- 2. 文章中の文字数
- 3. 文章中の文字(言葉)の使い方・選び方
- 4. 文章中の空間の使い方
- 5. 文章の説得力を高める
- 6. 読みやすい文章を書くコツまとめ
この流れで見てほしいと思います。
1. 文章を書く意識
読みやすい文章を書くには、文字の扱いばかりを気にしてしまいがちですが、もっと大事にする視点がいくつかあります。
文章を書くのに、特別で厳格なルールはないですが、意識するポイントが違ければ、やっぱり読みにくい文章になってしまう。
いくら文字単体の読みやすさに力を入れても、結局は読みづらい…。
そのため、文章を書く意識、全体を通して読みやすくするためのコツを最初に見ていきたいと思います。
「書き手」と「読み手」の会話になっているか
文章とは、文字や単語を集めて、意味を加えて相手に伝える形にしたもの。
文章を書いていると、自分が伝えたい内容がいっぱいあることで、相手の気持ちを無視して一方的に伝えようとしてしまいますが、それではダメなんです。
文章は相手に無理やり押し付けて読んでもらうものではなく、「書き手」と「読み手」の会話にならないといけない。と私は思っています。
どのような意味かと言うと、
例1:会話になっていない場合
私はブログが好きで、これで飯を食べてる人間で、毎月100万も稼いでいます。実は、小さいころから文章を書くのが好きで、それを仕事にしたらうまくいきました。今後もブログ飯をしていき、もっともっとお金を稼いでいきたいです。
例2:会話になっている場合
あなたは文章を書くのは好きですか?私は好きなのでブログを書き続けています。嬉しいことに、これで収入を得られるようになりました。もし、文章を書くのが好きなのであれば、ブログでも十分稼ぐことができます。
例1と例2の何が違うかと言うと、読み手を意識して「書いている」か「書いていない」かの違い。
また例え話になってしまいますが、相手の自慢話や、相手の近況ばかりを聞き続けるの、実は辛かったりしませんか?
他にも、友人と楽しく話していた時、別の誰かが乱入して別の話題になってしまった時、急につまらなくなる事はありませんか?
文章は「書き手」と「読み手」、あなたとユーザーさん2人だけの会話であり、それがどっちかに偏ってしまったり、第三者が入ってきて2人の会話でなくなってしまった場合、急に読みづらい・つまらない文章となる。
会話でなければ、一方的な情報提供と同じになってしまうため、読みやすい読みづらいの遥か先、左から右へ素通りしてしまうような文章(情報)になってしまいます。
「いや、文章で会話なんて無理でしょ!」と思われるのは当然。
web上に書かれた文章は、ユーザーさんごとに内容を変えられず、掲載されている文書をそのまま読むしかできないため、直接的な会話は難しいです。
しかし、これだけ多くの記事がweb上にある中で、一方的な文章を送りつける形は、ユーザーさんに選んでもらえない。
実際の会話は難しくても、相手を意識した、会話ができる文章を作っていく必要があると思っています。
また、文章の読み手は、目で追って文章を見ているだけでなく、文章を心の中で読みあげながら、心の声で会話をしています(意識している方は少ないと思いますが)。
書き手「文章を書くの好きだからブログが好きなんです。」
読み手「へ~だからこの人ブログやってるんだ(心の声で会話)」
書き手「文章を読みやすくするために、難しい漢字は使わないようにしています。」
読み手「あ、だからスラスラ読めるのね(心の声で会話)」
もしこれが、一方的で息も付けないような文章になっていると、最初は書き手と読み手が同じスタートラインにいたのに、いつのまにか書き手だけが先に進んでしまって、声も届かない距離に進んでいることもある。
置き去りにされる、声が届かない、こんな状態では、読みにくいと感じてしまいます。
文章の良し悪しだけが、文章の読みやすさではない事を、覚えてもらえると嬉しいです。
つじつま・文脈は合っているか
つじつま・文脈が合っていないと、読み手は読みづらさを感じてしまいます。
例1:私は文章が大っ嫌いです。昨日も10,000文字のブログを書きました。
例2:私は文章が大好きです。昨日も10,000文字のブログを書きました。
例1は、大っ嫌いと言っておきながら、大量の文章を書いており意味が繋がらないため「なぜ?」と読みながら考えてしまう。
例2だと、文章を書くのが好きなので、10,000文字を書いたのも納得がいきます。
このように、書き手が言っていることの前後関係のせいで、意味が繋がらない場合、途中途中で読みながら考えなくてはいけないため、非常に手間を感じさせられる。
脳はできるだけカロリーを消費しないようにセーブしてくるため、単純な文章なのに何度も考えさせられると、読みづらいと感じて、すぐに別の記事へ移動されてしまいます。
読みやすさは、文章の前後関係が繋がり、1本道のようになっている事が求められます。
文章を読む途中途中で、枝分かれした道が出てきたら、どこに進んだらいいか分からず、読みづらさが発生。
つじつま・文脈が合う事は、読みやすさを確保するために必要な意識だと思います。
2. 文章中の文字数
ここからは、読みやすい文章を書くコツの実践的な内容を見ていきたいと思います。
最初に見ていきたいのは、文章中で使われる文字数。
文字数の全体目安
読みやすい文章にするためには、文字数にも気を付けたいところ。
多すぎても読み手が疲れてしまうので、適度な文字数(文章量)の目安を知っておきたいですよね。
文字数が多すぎる=悪い、と思うのはまだ早すぎて、読み手にとって必要な情報が入っていれば、もちろん多くても問題ありません。
しかし、「SEOのため!」という考えの元、単純に文字数だけを増やして、引き伸ばす形はオススメではありません。
文字数の全体の目安としては、
2,000文字 → 1つのテーマを説明するのに最低限の目安
5,000文字 → テーマに関連した情報も入った基本の目安
10,000文字 → 関連情報も十分に入り読み手が満足いく目安
もし、20,000文字、30,000文字となると、かなり量が多くなってくるので、よほど重要なテーマだったり、説明する内容が多くなければ必要ないかもしれません。
そのため、基本の5,000~10,000文字を目安に、文字数を整えていく形がオススメです。
A4原稿用紙1枚に換算すると何枚分になる?
word(ワード)を使うと1行40文字(文字サイズ10.5)が入り、35~40行で計算すると、1,400~1,600文字になるので、以下のような枚数だと計算できます。
2,000文字 → A4原稿用紙1枚分
5,000文字 → A4原稿用紙3~4枚分
10,000文字 → A4原稿用紙5~6枚分
文章中の文字数は40文字(1行)~120文字(3行)
文章を書くとき、1段落の中で文字を多く入れすぎないのが、読みやすいコツ。※ 段落とは、文章の区切りのこと。
1段落で文章が長すぎる&文字が120文字以上(3行以上)
文章を読みやすくするためには、様々な方法があります。どれも効果が高く実践的、さらに誰でも簡単にできるので、試してみるのがオススメです。また、読みやすい文章にするためには、文字数にも気を付けなければいけません。読みづらさがあればユーザーさんの直帰率が高くなり、結果的にアクセスが増えないブログとなります。ブログで収入を得たい場合には、文章の読みづらさは避けなければいけない問題。確実に対策しておくべき内容なので、このページでぜひ読みやすい文書を書くコツを学んでほしいと思います。
このパターンだと、一気に読む必要があり息が付けないのと、1段落にテーマが複数入っていることもあるため、何が言いたいのか分かりづらくなる。
また、文字の塊を見せられることで、読む気も失せてしまう…。
1段落の文章が適切で読みやすい範囲&文字が100文字前後(3行以内)
文章を読みやすくするためには、様々な方法があります。どれも効果が高く実践的、さらに誰でも簡単にできるので、試してみるのがオススメです。
また、読みやすい文章にするためには、文字数にも気を付けなければいけません。読みづらさがあればユーザーさんの直帰率が高くなり、結果的にアクセスが増えないブログとなる。
ブログで収入を得たい場合には、文章の読みづらさは避けなければいけない問題。確実に対策しておくべき内容なので、このページでぜひ読みやすい文書を書くコツを学んでほしいと思います。
1段落ごと、適度な範囲で収まっており、読みやすくなっている。
段落を少し分けただけで、こんなに読みやすさが生まれるなんて、面白いですよね。
文字数も、1行分の約40文字前後から、3行の約100文字前後あたりまでに収めると、読みやすいです。
1段落の中で1つのテーマ(言いたい事)に絞って伝えることが読みやすさに繋がってくるので、実践するとさらに読みやすくなる文章が書けると思います。
3. 文章中の文字(言葉)の使い方・選び方
読みやすい文章は、文字(言葉)の使い方にまで意識が向けられています。
どんな使い方が良いのか、見てみましょう。
難しい言葉は使わない
難しい言葉には使いどころがあり、誰に向けて文章を書くのかにもよる。
ブログ初心者のために文章の書き方を記事にした場合を例に見てみたいと思います。
例1:難しい言葉を入れたパターン
ブログを書くにはSEOを意識してキーワード重視の文章を書くと、多くのPVが稼げるようになります。
例2:難しい言葉が無いパターン
ブログを書くには、みんなが検索する回数の多いテーマや言葉を軸にした記事で書くと、たくさんの人があなたの記事を閲覧してくれるようになります。
例1で、SEO・キーワード・PVといった単語が出てきましたが、ブログ初心者の方が、これらの意味を知らない場合は、ブログ初心者向けと言っておきながら、ブログ初心者が見たらチンプンカンプンな文章。
例2であれば、SEO・キーワード・PVを知らなくても、意味が分かる内容となっているので「読みやすい!」と思ってもらえます。
難しい言葉を使わない、これが読みやすさを生み出すコツです。
しかし、読みやすさは「誰に向けた文章か」によって変わってくるため、その人向けに書かれた文章が、もっとも読みやすくなります。
文章を読んでくれる人を、どれだけイメージできているか、ここが読みやすい文章を作るうえで、重要なポイントだと思います。
漢字を少なくしカタカナとひらがなを多くする
難しい言葉は使わずに、読みやすくするコツとしては、2つのポイントがあります。
- カタカナを使う
- ひらがなを使う
例えば「直接」と言う言葉を変換してみます。
直接:ダイレクト(カタカナ言葉)
直接:ちょくせつ(ひらがな言葉)
「直接」という単語であれば、カタカナに変換した方が良さそうですね。
難しい:ディフィカルト(カタカナ言葉)
難しい:むずかしい(ひらがな言葉)
「難しい」という単語であれば、ひらがなに変換する方が分かりますね。
それではもう少し、文章で例を見てみたいと思います。
例1:漢字だらけの文章で読みづらい文章
文章は漢字を多く使うと難しく読みづらい。もっと直接的に相手へ伝える文章を書く必要がある。
例2:カタカナやひらがなで読みやすくした文章
文章は漢字を多く使うとむずかしく読みづらい。もっとダイレクトに相手へ伝える文章を書く必要がある。
どうでしょうか、ちょっとの差かもしれませんが、漢字が続かない例2の文章の方が、読みやすいと思います。
ブログでは、ず〜っと文章が続くため、漢字が多いとさすがに読み手も疲れてしまう…。
ちょっとの気遣いがあるだけで、読み手が読み進めてくれる確率が高まるため、「漢字が多いかな?」と思ったら、所々でカタカナやひらがなに変換させてあげるのが読みやすい文章を書くコツになります。
句読点の入れ方
句読点の入れ方次第で、文章で言いたい事の意味が変わったり、読みづらくなってしまいます。
例1:句読点がおかしい文章
読みやすい文章を見分けるポイントは句読点の、入れ方に注目したい。
例2:句読点が正しい文章
読みやすい文章を見分けるポイントは、句読点の入れ方に注目したい。
この例文では「句読点」の「入れ方」という2つの言葉が繋がることで、初めて意味が見えてくる文章なのですが、例1のように句読点で繋がりを断ち切ってしまうと、意味が曖昧になる。
意味が曖昧になると、読みづらさへと変化…。
「、」「。」を適切な箇所で使わないと、読みづらい文章となるので、十分注意したいですね。
文字の大きさ(フォントサイズ)
文字の大きさは、読みやすさに大きく影響します。
12pxの文字
14pxの文字
16pxの文字
18pxの文字
どのサイズがあなたは読みやすいと思いましたか?
自分が読みやすいと思ったサイズの、一つ上のサイズを目安にしましょう。
自分が感じた心地よいサイズと、他人から見た心地よいサイズは違います。
特に、ターゲットの年齢が高くなればなるほど、目が悪い方が多くなっているので、自分自身が十分なサイズではなく、相手から見て十分な文字のサイズを確保。
文字のサイズ一つとって見ても、読みやすさは大きく変わるため、文字サイズも意識したい読みやすさのコツに含まれます。
見出しの活用
ブログのような文章と、小説のような文章では大きな違いが1つあります。
それは、見出しの数。
ブログ:小見出しがたくさんあり区切りが多い
小説 :一気に文章を続けて読むため見出しは無い
ブログなど、インターネット上の記事を見る方の多くは、自分が欲しい情報を探すために検索して記事へ訪れています。
- 時間が無いからすぐに欲しい情報を見つけたい
- 欲しい情報が無いならすぐ別の記事を探す
- 何の情報が書いてあるか分からないならすぐ次へ移動する
このような特徴が、インターネットで情報を検索する方に見られる特徴です。
そのため、小説のような、物語を順を追って見ていくような文章の書き方だと、欲しい情報がここにあるのか、先にどんな情報があるのかが分からない。
時間を無駄にしたくないので、すぐ別のブログへ行ってしまいます。
ブログなどの記事では、小見出しを適度に入れながら、情報を分割する形をとると、読みやすい文章を書けるようになります。
あえて、感情に訴えかけるような文章にしたい場合は、小説のような、文章を続けて見せる形が効果的です。
箇条書きの利用
箇条書きの利用は、読みやすい文章を書くコツと言えます。
例えば、下記のような文章があったとします。
例1:箇条書きにする前
箇条書きの特徴は、物事を簡潔に伝えられ、文章を短くし、読みさすさを向上させてくれる効果があります。
例2:箇条書きにした場合
箇条書きの特徴は、
・物事を簡潔に伝えられる
・文章を短くできる
・読みさすさの向上
このような効果があります。
文章だと長くなってしまったものが、箇条書きを利用する事によって、書き手はシンプルに伝えたい内容を伝え、読み手は内容が把握しやすいので読みやすいと感じる。
文章がちょっと長いかな?と思ったら、迷わず箇条書きを試してみるのがオススメです。
擬音語・擬態語を活用する
擬音語・擬態語も、読みやすい文章にするコツの1つ。
擬音語とは、人・動物、または自然界の音や物音。
→ガンガン、サクサク、ビリビリ
擬態語とは、生き物・物の状態や身振りを表した表現。
→すべすべ、まったり、ひしひし
文章中で擬音語・擬態語を使った例を見てみたいと思います。
例1:擬音語を使った文章
雷がドカーンと鳴っていますが、僕は今、ブログを書いています。
例2:擬態語を使った文章
最近ブログを始めた友人が、ニコニコしながら、ブログ飯の話をしてきた。
擬音語・擬態語どちらでもいいですが、文章に表情が出てきた気がしませんか?
マニュアルや仕様書だと、感情の無い能面のような印象になりますが、擬音語・擬態語が使われると、一気に読み手が受ける印象が変わってきます。
面白さを出すこともでき、この先も読んでいきたい=読みやすい文章にもする事ができるので、コツの1つとして覚えてもらうのがオススメです。
感情を言葉(感嘆語)として入れる
読みやすさとは、単純に優しくて分かりやすくて丁寧な文章の事だけじゃない。
伝達率?浸透率?と言えばいいのでしょうか。
読み手が感じる感情、書き手が思う感情を、そのまま言葉として表現することで、読みやすさを作る事ができます。
例1:驚きの感情
Googleのアップデートがあり、アナリティクスを見たら結構PVが下がってて「うわぁ」ってなった。
例2:納得の感情
人気ブロガーにアクセスアップの方法を聞いたら、納得の答えが返ってきて「なるほどね〜」と思った。
共感できる感情が入っていると、書き手と読み手の心理的距離が近づくため、それが読みやすさにも変化。
相手の納得が読みやすい文章を書くコツにもなることを、覚えてもらえるといいかもしれません。
4. 文章中の空間の使い方
文章が続くだけだと、変化もなくて、読み疲れが発生。
強調する部分は強調したり、リストやテーブル表示、または文字に変化をつけたりすることで、読みやすさを高める事ができます。
下記では、文章中の空間を使ったり、文字の変化によって読みやすさを向上させる例となります。
空間の使い方、文字の変化
フォントサイズが太くなる、アンダーラインが入る、色が赤・青・緑なども効果的
- 箇条書き1
- 箇条書き2
- 箇条書き3
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 項目が入ります。 | 詳細が入ります。 |
囲み装飾
囲み装飾を使った例。
- 囲み装飾
- 囲み装飾を使った例。
こういった変化を使い、文字だけを見るのではなく、全体の空間を見ながら文章を作っていきます。
読みやすい文章を書くには、単純な文章の書き方だけではなく、空間を使ったデザイン性も求められるもの。
記事ページ全部を使って、読みやすさを演出する事が大事です。
色に関しての注意事項として、多色ではなく使うのであれば2〜3色にまとめると、綺麗にまとまった印象を作れるため、なんでも使いすぎない方がいい。と覚えてもらうといいかもしれません。
5. 文章の説得力を高める
読みやすさとは、納得度にも置き換えられます。
読んでいて、この情報は本当に正しいのか?という疑問だらけの文章は、読みやすいとは言えません。
そのため、文章の説得力、納得を高める情報を入れるのが、読みやすさに繋がるコツとなります。
根拠のあるデータや補足情報を入れる
疑問を読み手に感じさせないために、根拠のあるデータや補足の情報を入れていきます。
例1:文章の根拠を示すデータ・確認先が無い
ブログのドメインで多いのは「.com」です。
例2:文章の根拠を示すデータ・確認先が有る
ブログのドメインで多いのは「.com」です。※ 調査結果:【2019年まとめ】ブログを始めるなら見ておきたい、人気ブロガー10個の調査結果
根拠のあるデータが書かれていない例1と、書かれている例2では、圧倒的に例2の方が、真実味が増した文章となっています。
もし、何かの調査結果や、数値を元に説明されている文章に、その根拠や補足の情報がなければ、信じていいの?と疑いが出てきますよね。
この疑いによって、その後の文章に対しても、疑いを持ってしまい、すんなりと読めなくなることで、読みづらい文章となる。
読みやすい文章を書くコツは、読み手に疑問を感じさせないことです。
自分の個人的な情報を小出しで入れていく
読みやすい文章を書くには、文章の中でいかに、信頼を感じてもらえるかが大事。
これは「根拠のあるデータや補足情報を入れる」ことと同じ意味となりますが、今回はやり方が少し違います。
「根拠のあるデータや補足情報」を入れるのが1つ目で、2つ目は自分自身の個人的な情報見せていくこと。
例えば、書き手がどんな人なのか、どんな想いで書かれている文章なのか分からない場合、読み手は単純に文章を読むことだけで終わってしまいます。
しかし、書き手の個人的な情報を少しずつ入れた文章だと、読み手が書き手を想像し、興味を持って読んでくれるようになります。
「この人の文章を読みたい!」と感じてもらうと、文章の読みやすさにも繋がってくる。
例1:書き手の情報が無い
ブログを頑張ると収入を得られるようになり、脱サラリーマンも夢ではなくなります。
例2:書き手の情報が有る
私は会社でパワハラを受けて、仕事が本当に辛かったです。しかし、文章を書く事が好きなのでブログをやり出したら、いつのまにか本業よりも稼ぐ事ができ、今では脱サラしてブログで生活しています。
例1はただの事実だけですが、例2は事実に根拠やその背景が分かる情報が入っているため、より真実味が増した文章となる。
信用ができそうだと思える文章は、スラスラと読んでいく事ができ、これが文章の読みやすさにも繋がってくるんです。
人は人という存在に惹かれるため、書き手の情報をうまく入れていくことで信用を得られ、読みやすい文章を作る事ができます。
6. 読みやすい文章を書くコツまとめ
- 1. 文章を書く意識
- 2. 文章中の文字数
- 3. 文章中の文字(言葉)の使い方・選び方
- 4. 文章中の空間の使い方
- 5. 文章の説得力を高める
この5つを見て頂きましたが、いかがでしたか?
「ん〜まだ分からない…。」と思われても全然大丈夫。
これは、私が考える「読みやすい文章を書くコツ」であり、世の中にたくさんある方法の中の1つです。
そのため、こんな方法もあるんだな〜くらいで覚えて頂くといいかもしれません。
全部は覚えなくてもいいですが、あなたには1つだけ覚えてもらいたい事があります。
それは、読みやすい文章とは、文章の書き方だけを示しているのではないということ。
特に、書き手が読み手を意識することが、読みやすい文章を書くためのコツなので、この意識だけは忘れずにいてほしいです。
文章をチェックする便利なツール
読みやすい文章を書くためには、何度も何度も調整を続けて、読みやすくしていく必要がありますが、調整を続けて良い文章にしていく事を推敲(すいこう)と言います。
推敲?という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、校正なら聞き覚えがありませんか?
推敲(すいこう) → 何度も調整して文章を良くしていく
校正(こうせい) → 推敲の後に誤字脱字や基本的なチェックをする
推敲のあとに行うのが校正です。
読みやすい文章を書くためには、推敲することが必要不可欠。
推敲をすると思うと難しく感じてしまいますが、「読みやすい文章を書くコツ」の章で見てもらった内容を実践頂ければ問題ありません。
ただ、何かしらの基準をもって文章を直したい…と思う場合、推敲が簡易的にできる無料ツールがあるので、それを使ってみるのもオススメです。
1~3の無料の推敲ツールは、機能的にはほぼ同じで、検討すべき言葉や文章の指摘をしてくれます。
例えば、「ツイッター」と書いてあった場合は「Twitter」という固有名詞があるよ、と教えてくれたりするんです。すごく便利ですね。
推敲ツールの中で、1つだけ毛色が違うのが、4つ目の小説形態素解析CGI(β)。
このツールは小説系の文章をチェックする無料ツールなので、通常のブログなどには適さないのですが、以下のようなことが分かります。
- かな:漢字の比率
- 文章のテンポ
- 使用されている文章手法
など、他の推敲チェックツールでは、「文章」という部分を中心に見てくれますが、小説形態素解析CGI(β)では「文章の流れ」を見てくれます。
そのため、できるなら、1~3のどれか1つと、4の小説形態素解析CGI(β)も使ってもらえると、あなたの文章がより読みやすくなると思います。
それでも読みやすい文章が書けるか不安な場合は?
読みやすい文章を書くための情報は色々分かったけど、やっぱり不安…。
そんな時は、最後に下記の2つを試してみてください。
- 音読をする
- noteを真似る
それぞれを詳しく見てみたいと思います。
音読をする
音読とは、実際に声を出して文章を読み上げること。
音読がスラスラできないような文章だと、それは読みづらさを生んでいる証拠です。
読み手は文章を読むときに、わざわざ声に出しているわけではないですが、心の中で文章を読み上げています。
心の中だと気づきにくいことも、音読だと気づける部分もたくさんあるため、音読がオススメなんです。
noteを真似る
noteとは、株式会社ピースオブケイクさんが運営している、クリエイターの情報発信と、クリエイター同士の交流を提供したプラットフォーム。
ブログが書けたり、自身のノウハウを販売し、収入を得ることもできます。
なぜ私が、noteを真似ることをオススメしたいかと言うと、2019年9月には月間アクティブユーザー数(MAU)が2000万人に達している、多くの人が認めるサービスだから。※ noteの月間アクティブユーザーが2000万人を突破しました―8ヶ月で利用者が倍増
noteは文章が主体となっているため、
- 使いやすさ
- 読みやすさ
このポイントが非常に考え作られていて、下記の内容を真似るだけでも、読みやすい文章になります。
1行:40文字前後まで
font-size: 18px;
line-height: 36px;
margin-top: 36px;
margin-bottom: 36px;※ 2020年1月22日現在のnoteの文章の仕様
もし、見た目から入っていきたい、何か読みやすくする基準が知りたい場合は、noteの仕様を真似る形がオススメです。
最後に。
読みやすい文章を書くには、いくつかコツはありますが、何度も何度も調整して、何度も何度も読み直して、繰り返し調整して初めて手に入れられるものだと思います。
そのため、文章を書く事、読み手に喜んでもらえることに貪欲になって頂き、何度も調整をして頂くといいかもしれません。
あなたが文章に込めた想いは、必ず読み手に伝わります。
どうかあきらめずに、文章を書く事を楽しみながら、読みやすさに挑戦して頂けると嬉しいです。