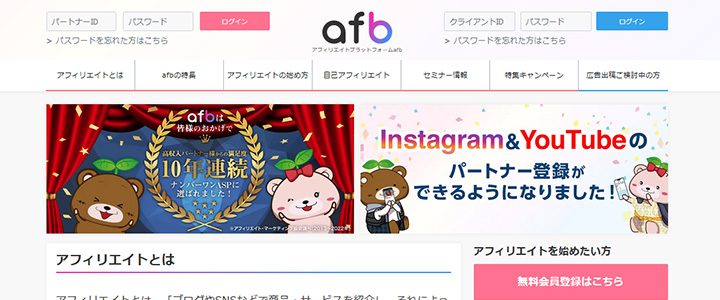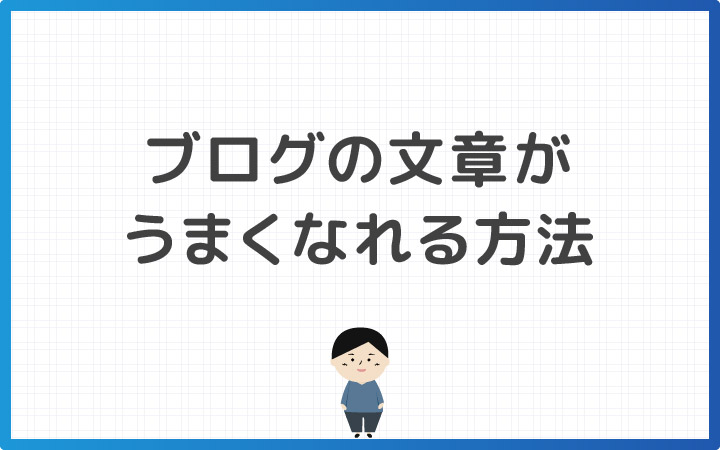
文章の「うまい」と「へた」って、見た目では大きい変化が無いのに、違いを感じるので不思議ですよね。
当然、うまい文章の方が仕事もスムーズに進み、お金も稼ぎやすくもなる。
義務教育で国語の点数がわるかったとしても、この不思議で魅力的な「うまい」と「へた」をじっくり考えて、ブログの文章がうまくなれる方法を見ていきたいと思います。
この情報が、少しでもあなたのお役に立てられれば嬉しいです。※ webに掲載する文章に関してのお話しになります。
すぐに「うまい」を手にする方法を知りたい場合は、「文章を「うまい」と思ってもらう方法」を見てくださいませ。著者:osugi(@osuuuugi)
文章が「うまい」とは?
「この文章うまいよね!」と言われる記事では、何とか法を使っている、言い回しを変えているなど、テクニック的な話になりがちです。
しかし、文章が「うまい」と思ってもらう要素は、テクニックだけではありません。
ユーザーさんはそもそも、何をしにあなたのブログを見にきてくれたのか。
それは、欲しい情報が掲載されている可能性があるからだと思います。
最初から文章がうまい人のブログを探しているユーザーさんであれば別ですが、キーワードを入力して検索しているユーザーさんにしてみたら、文章の良し悪しよりもまず、欲しい情報があるかどうか。
文章の良し悪しは二の次だと言えます。
もし、ユーザーさんが欲しいと思っていた情報がなければ「なんだよー、ないじゃん。」となって、期待を裏切ることで、文章に対してもマイナスな感情を抱かれてしまう。
それとは逆に、ユーザーさんが欲しい情報があり、不安や問題をあなたのブログで解決できた場合、感謝とともに信頼性を得られて、文章への好感度も上がって「うまい」と思ってもらいやすくもなります。
この事を考えると、テクニック的な話だけで文章の「うまさ」は説明することができず、ユーザーさんの目的と掲載情報のマッチング度や、問題解決ができた影響力なども考えるべきではないのか。
そのためこの記事では、文章のうまさを「ユーザーさんの感情や行動へ良い影響を与える要素」と定義した上で、考えていきたいと思います。
「うまい」を考える前に、文章は何で出来ているのか確認
文章の「うまい」を考える前に、文章とは何で出来上がっているのか考えてみたいと思います。
- 単語
- 単語の意味
- 単語の組み合わせ(言葉)
- 文脈(繋がり)
単語が組み合わさり、複雑な意図を表現して文脈という時系列の繋がりが文章を形作る。
文章とは、こんな解釈ができるかもしれませんね。
そして、大元の単語はどこから出てきたのかと言えば、書き手が今まで経験して得てきた情報・知識・感情などの記憶からです。
まったく知らない情報に関しては、うんうん唸ってみたり、一生懸命考えてみたとしても、まったく出てきません(残念なほど…)。
だからこそ文章とは、全部あなたの中に眠っていた記憶が、表にでてきた存在だと意識して頂きたいです。
文章の「うまさ」を具体的な言葉で表わしてみる
「いや~この書き方最高!」
「こんな文章書きたいな。」
あなたがお仕事やプライベートで文章を扱っているなら、こんな気持ちを感じたことはないですか?
しかしこの「うまい」と感じているもの、何を「うまい」と言っているのか具体的には表現しずらいですよね。
統一感があるとか、言い回しにセンスがあるとか、人によって様々な解釈もある。
そこでまずは、当社で文章のお仕事で活躍している3人のメンバーへ、「うまい」と思う文章について聞いてみました。※ 社内の身近な人の意見を聞いてみたので一つの意見として。
__
文章のお仕事歴:3年未満のFさん(女性)
文章がうまいとは? → 共感や憧れを感じること
難しい話を、知らない状態でも理解できるような優しい内容だったら。
すらすら読めて、飽きさせないリズムがある。
読んでて楽しい。単純に笑えるってことだけじゃなくて、引き込まれるような内容で、自分も似てる体験が書いてあると「そうだよね~」ってなる。
憧れや共感もあると「うまい」って感じます。
文章のお仕事歴:4年目のSさん(男性)
文章がうまいとは? → その場にいなくても言葉だけでイメージさせてくれる
文字だけで、説明された感情や場面がイメージできたり、思い浮かべられるように書かれていると「うまい」と思う。
文章のお仕事歴:10年以上のベテランIさん(男性)
文章がうまいとは? → 書き手が十分な理解のもと、分かりやすく書かれた文章。
分かりやすいか、そうでないかが一番。
下手な文章は意味が通っていないことが多い。
ただ筆者自身が意味を理解していない(インプット下手)なのか、
筆者が意味を理解しているけど表現がダメ(アウトプット下手)という大きく2つのタイプに分かれると思う。
__
ライティング歴でも解釈に違いがありました。
しかし、学んできた環境や、自分自身の大事にしている事が誰もが違うので、考えている事は違って当然。
そんな中でも、3人に共通しているのは、3人とも書き手の情報が文章によって、しっかり伝わったからこそ、うまいと思えていること。
情報が伝わってなかったら良い評価なんて、できないですもんね。
たとえば料理もそうで、自分だけ食べるなら適当に作りますが、食べてくれる人がいれば、その人に美味しいと思ってもらえるように作る。
おいしさや、相手への気持ちなど、料理も同じく「伝わった」ことを目指しています。
この解釈を「文章」に対して当てはめてみると、書き手がユーザーさんに喜んでもらうため、情報を伝わるようにしている事の全てが「うまい」と言われる要素に該当するとも言えます。
喜んでもらう、伝わる、こんなキーワードが文章のうまさにも関係してくることが、なんとなく分かってきました。
これだとまだ曖昧なので、もう少し何が「うまい」と思わせているのか分解してみます。
文章の「うまさ」をもう少し具体的にしてみる
ユーザーさんに伝わることで「うまさ」を感じてもらえますが、それはどういったことなのか。
伝わったのであれば、ユーザーさんの方では、目的が達せられたり、何かしらの結果が見えているはずです。
そのため、伝わった結果、何が起こったのかを知ることで「伝わった」を具体的にしてみたいと思います。
伝わった結果①:知りたい情報を知る事ができた
まず「伝わった」の大前提としては、ユーザーさんが知りたい情報があり、尚且つそれが、ユーザーさんが分かる説明で書かれているのが大事だと思います。
知りたい情報とは、ユーザーさんの検索意図を理解した情報。必要な情報を全て揃えなければいけない。
分かる説明とは、難しい言葉ではなく、ユーザーさんが日常会話で使うような聞き慣れている言葉を使った、普段通りを感じられる文章。
特に文章を読むのは、欲しい情報をすぐ手に入れたい衝動の中、どこに欲しい情報があるのか分からずストレスがかかるもの。
そのため、すぐに欲しいという衝動を邪魔する難しい言葉が使われていたり、普段聞き慣れない言い回しを書き手が自己満足的に使ったりして、学校で勉強をしているような印象を作ってしまうと、文章を見るのが嫌々になってしまうので注意をしておきたいです。※ ユーザーさんはすぐに情報が欲しいので、単語の意味を別で調べたり、すぐ目的にたどり着けないような状態にするべきではないと思っています。
最適化された情報によって、ユーザーさんが知りたいことが知れた時に「伝わった」が発生します。
伝わった結果②:解決したい事が解決できた
それぞれ状況はあると思いますが、ユーザーさんが何かを調べたいと思ったら、そこには最終的なゴールとして、問題の解決が入ってきます。
情報が欲しい理由は、ただ単に情報を手に入れたいのではなく、手に入れて問題を解決、またはユーザーさん自ら良い意思決定をするため。
情報によってユーザーさんのしたい事が出来るようになると、「情報の信頼性」が「文章の信頼性」へと変化し、うまい文章だと思ってもらえるようになります。
伝わった結果③:書き手の意見や考えを感じて信頼できた
インターネット上では、同じ情報が山ほど存在しています。
そんな状況の中では、何を信じたらいいのか分からないので、何が書いてあるかより、誰が書いているのかが重要になってくる。
誰が書いているのかを見せるためには、書き手自身の意見などを盛り込み、誰がその情報の正しさを保証しているのかを示すことで、根拠がさらに増す。
必要な情報があり、それらを信じていいのか根拠も加われば「伝わった」をさらに加速させることができます。
必然的に文章の「伝わった」が発生して、文章もうまいと感じてもらいやすくなる。
3つを見て頂きましたが、これらはブログ記事を書く上で基本と呼べるもので、全てがユーザーさんへ伝わる文章にするための考え方。
つまり、伝わる基本を守るだけで、うまい文章が作れるということ。
もしうまい文章を作るために、
- 国語力がないとダメ
- 教養がないとダメ
- 地頭がよくないとダメ
- 天才じゃないとダメ
これらが必要じゃないとダメだと思っているなら、そんな考えは吹き飛ばしてしまいましょう。
例えば、超人気ブロガーさんだからと言って、自分勝手でユーザーさんを全く無視した文章を書いたらどうでしょうか?
その文章を見た多くのユーザーさんは、情報が伝わらなかった関係で、文章を「うまい」だなんて思わないと思います。
有名コピーライターさん、どこかの大手出版社の編集者さん、これらの方々も、ユーザーさんに伝わらない文章を書けば、うまいなんて思ってもらえません。
伝わるを極めていけば、うまい文章が書けるようになるので、この意識だけは忘れないでほしいです。
文章を「うまい」と思ってもらう方法
ブログの文章が「うまい」と思ってもらうため、ここから具体的な方法について見ていきたいと思いますが、その前にもう一度以下の3つを意識してほしいです。
- ユーザーさんは文書が「うまい」か「へた」かは二の次
- 大前提は欲しい情報があること
- 情報が正しい形で受け止められて伝わること
例えば「伝えた」と「伝わった」には大きな違いがあり、「伝えた」は書き手が一方的に伝わった「つもり」になっている言葉で、文章を書いた目的はまだ達せられてない状態。
「伝わった」は、情報の受け取り側がしっかりと受け止めてくれた状態なので、情報のキャッチボールが成功したことを示しています。
一方的に情報を押し付ける意識だと、まったく文書をうまいと思ってもらえないので、お互いが両想いになるような情報の渡し方をしたいと思います。
そのため、以下のような方法で「伝わった」を作れるよう、対策してみましょう。
気を付けるポイントは以下の5つ
- 情報への理解
- 日常を感じてもらう
- 文脈で適正な流れを作る
- 信頼の根拠を示す
- 書き手の存在を示す
文章の「うまさ」をもう少し具体的にしてみるで書かせてもらった内容を、さらに分解した内容がこちらになります。
情報への理解
情報への理解とは、単語や言葉だけではなく、ユーザーさんの検索意図や動機など、文章を書くことに関わる全ての意味を理解すること。
完全に理解することなんて出来ないのですが、理解に努めることで、その情報があなたにとって、本当の意味で扱えるようになります。
情報への理解が10% → 10%以下でしかアウトプットできない
情報への理解が90% → 90%前後、もしくは90%以上でもアウトプットできる
もし、インプットした情報を、そのまま何も意識せず使った場合、意味やなぜそれが存在しているのかなど、理解していないものを使っているので、ユーザーさんからその事に対して質問されても、明確な回答もできません。
例えるなら、インスタントラーメンの作り方も見ず、茹でることもせず、そのまま食べるような感覚(そのまま食べるのが好きな方もいるかもしれませんが…)。
正しい作り方を理解すれば美味しいラーメンが作れるのに、どうやって作るのか、何をすれば美味しくできるのか考えもせず、存在するそのままを使ってしまった例です。
これはですね、絶対にもったいないお化けが出てくるパターン。
情報への理解とは、扱う情報に対して、どれだけ考えたのか、その総量ともいえます。
使い方を知らない未知の道具を渡されても扱えず、逆に理解が深くなればなるほど、自由自在に扱えるようになる。
素人と達人を想像すると分かりやすいかもしれませんね。
あなた自身が分かっていない、理解していないのであれば、ユーザーさんに対しても分かる言葉で説明できないため、「伝わった」を達成することができず、「伝えた」で止まってしまいます。
情報を扱うのであれば、ユーザーさんに文章が「うまい」と思ってもらえるよう、とことん理解に努めてから、初めて使えるようになると思っておきましょう。
ポイント!
誰に向けた文章なのかによっても変わってきます。
伝えたいことに対して、まったく事前情報がない人に届けるのであれば、ある程度の理解で文章を書いたとしても、悪い言い方をすればユーザーさんはその情報の良し悪しを判断する情報すらないので、まだ大丈夫だと言えます。
しかし、ある程度の事前情報をもったユーザーさんに対して、すでに持っているような知識を振りまいても何も反応してもらえません。
情報への理解度が、ユーザーさんよりも深かった場合、新たな情報を文章としても書けるので、反応してもらえる。
浅い知識だけだと、周りには競合だらけであり、埋もれてしまうため、情報への理解度の深さは必須だと言えます。
情報を理解するための方法とは?
情報理解を深くするためには、いくつか方法があります。
あなた自身ですでに行っている方法もあるかと思いますが、私自身が文章を書くために行っている方法を下記に記載しました。
- マインドマップで頭の中を可視化
- 同じ情報を複数の視点から調べる
- 軸をズラして考える
どれも簡単なので、ぜひ試してあなたに合う方法があれば、取り入れてみるのもオススメです。
マインドマップで頭の中を可視化
マインドマップとは、頭の中で考えていることを書き出し、それぞれの繋がりを可視化すること。
手書きで行うこともあれば、ツールを使って出すこともできます。※ マインドマップってどんな形?と見た目だけを確認するのであれば、keysearch Betaを見ていただくと分かりやすいかもしれません。
例えば、
ブログの文章がうまくなりたい
→なぜ?うまくなりたいのか
→どうしたらうまくなれるのか
→うまくなった次はどうしたいのか
このような形で「なぜ?」と自問自答を繰り返し、根源を探していく。
文章がうまいと言われるためには、文章として書きたい対象に、深い理解がなければ、具体的な説明ができません。
マインドマップは、書きたい対象への深い理解ができるようになるので、とっても役立つんです。
書き出した内容がそのまま、文章の中にも取り入れられるので、文章を書くスピードも格段に早くなります。
同じ情報を複数の視点から調べる
ユーザーさんがあなたの書いた文章から、必要な情報を取り出したとします。
しかし、取り出したものの、なぜか納得いかず、別の方が書いた情報を見た時、ユーザーさんにマッチした内容が入っていた場合は、最初に見たあなたの情報の評価がガクンと下がる。
例え、自分としては知っているつもりであったとしても、ユーザーさんからすれば、あなたの情報への理解が薄いと感じてしまうんです。
せっかく見に来てくれたユーザーさんの期待を裏切ることにもなるため、マイナスイメージから文章が「へた」だと認識されてしまう場合も。
そのため、あなたが文章で書きたい情報に対して、他の人はどんな解釈で書いているのか、2~3人ほど見てみるのがオススメです。
私の場合は、何か専門的な情報がほしい場合、同じテーマについて書かれている本を2~3冊買って、情報の比較をしたりしています。
文章を書く時、どうしても自分の思考が優先されがちなので、自分が気づかないポイントはスルーしてしまうことが多い。
それらを少しでも減らすため、複数の視点から情報を調べて理解し、文章を書く事で「伝わった」にできます。
軸をズラして考える
完璧な人なんて、この世に存在しないと思っています。そして、全ての情報を知ってる人もいない。
自分が考えられたり思いつくことは、世界から見れば、ほんの一部でしかないんです。
ユーザーさんも何千何万何億人と存在しており、それぞれ趣味嗜好や信じて大事にしていること、ほしい情報も違ってくる。
千差万別という言葉がありますが、万差億別ともいえる状況が世の中には存在。
そんな状況の中、自分だけで考えられることでは情報としては足りないため、自分の意識を拡張するために、さまざまな軸をズラして考えてみることが大事です。
- 最高と最低
- 好きと嫌い
- 時間があるない
意識的に出せる情報でしか人は考えられないので、意識を拡張させる軸をいくつも持っていると、より深く情報を知る事ができるようになるんです。
日常を感じてもらう
日常を感じてもらうとは、ユーザーさんにストレスを感じさせないような日常を作り出し、より伝わる環境にすることです。
旅行などは非日常を体験するためのものですが、文章を見ることはユーザーさんにとって日常で当たり前の光景。
ユーザーさんの日常は、見たいものだけを見る傾向が強い(私自身もそうです)。
無理して見たくないものは見ませんよね(まったくもってそう思ってます)。
そのため、普段見慣れているものは、浸透率や理解度を早めることができますが、見慣れていないものをわざわざ見ようとするとストレスを感じます。
普段してないことは、すぐできないのと一緒で、今まで休日は12時まで寝てたのに、明日から朝5時起きなんて簡単できるものじゃない…。
これを文章に当てはめてみると、ユーザーさんが普段見慣れている・使い慣れている言葉や段落なども含めて、日常を感じられないと、たとえどんなに良い文章や情報だったとしても、ストレスを感じて嫌いな文章になる。
文章をうまいと思ってもらうには、ユーザーさんの日常を壊してはいけないんです。
日常を感じてもらうための方法とは?
ユーザーさんの日常を壊さないためには、
- 文章を届けたいユーザーさんが誰かを理解する
- ユーザーさんの普段を知る
この2つが大事かなと思っています。
文章を届けたいユーザーさんが誰かを理解する
誰に向けた文章か考えるのは基本だと思います。
これがないと、そもそも文章をどうやって書けばいいのか分かりませんよね。
当たり前かもしれませんが、明確に誰へ向けた文章なのか分からないと、どんな内容を入れればいいのか、どんな表現を使って書けばいいのか曖昧なまま書いてしまうことで、見る側からしたら「へた」な文章と感じてしまいます。
知らない誰かをイメージできなければ、あなたの身近にいる近しい人を想像するだけでも、かなり変わってくるので、誰に向けた文章かを必ず意識しましょう。
ユーザーさんの普段を知る
ユーザーさんの普段を知ることは、たぶん無理だと思います。
無理ではありますが、理解に努めることはできるので、ユーザーさんの普段をとことん考え意識してみましょう。
- この言葉、普段使わなくない?
- このタイミングだと、こんな感情抱くんじゃない?
- 上司じゃなく、友人や家族のような感覚を持ってもらえてる?
文章を読むことに対して、どれだけストレスを感じさせないかがポイントです。
特に、家族や友人と話している時、そんなこと言う?このような意識を持っていると、普段をイメージしやすいです。
文脈で適正な流れを作る
文脈で適正な流れを作るとは、文章単体、または文章の繋がりを通して「伝わった」を作り出すこと。
文章における文脈とは、文章の前後関係や時系列などが該当します。
例えば、
×な例:文章の繋がりや関係性が分からず意味が理解できない
前 ブログ書いたんだよねー。
後 あれってどうなってる?
〇な例:何があり、どうしている、このような繋がりが分かる
前 最近、副業をしたいと思ってるんだ。
後 そのためブログを書き始めてみました。
文章が「へた」だなと思うポイントの一つとして、文脈の最適化ができてないことが多いです。
意図して「へた」に書いていることは無いと思いますが、書いている途中は気付かず、いざ見直してみると誰であっても文脈が合わないことはある。
最低限、守っておきたい文脈は「何」が「どうなる」のか。
難しいことはする必要はなく、前後関係が繋がる文章を書くことで、ユーザーさんから「うまい」と思ってもらえる文章が書けるようになります。
文脈で適正な流れを作るための方法とは?
文脈で適正な流れを作るためには、
- 全体的な繋がりを作る
- 各章ごとの繋がりを作る
この2つを意識する必要があります。
全体的な繋がりを作る
まずは全体を通して文脈という繋がりを作ります。
何かを説明したり、伝えたい時は、効果があると言われている構成があります。
三段論法
主題 → 理由 → 証拠 → 結論
5W1H
だれが → いつ → どこで → なにを → なぜ → どのようにしたのか。
PREP法(プレップ法)
結論 → 理由 → 具体例 → まとめ
BEAFの法則
メリット → 論拠 → 競合優位性 → さまざまな特徴
他にも色々方法はありますが、どの方法を使えばいいのか?と迷う必要はありません。
結果的にどの構成を使っても、何が→どういう理由で→こうなったのか流れを表しているので、この大きな流れが作れていれば、全体的な文脈は大丈夫です。
各章ごとの繋がりを作る
文脈が適正かどうかは、文章単体では分かりません。
ブログであれば、3~7つほどの見出しがあり、その見出しごとで説明する内容は違ってきますよね。
そして、各見出しの中には一章分ごとに何行か文章が入っているため、一章ごと全ての流れを見て、文脈が保たれているかを確認します。
各章ごとでは、何を説明するかテーマが決まっていると思うので、文章の繋がりが「ある」か「ない」かだけでなく、テーマから外れていないかも確認するのも、文脈を適正にするためには必要です。
信頼の根拠を示す
信頼の証拠を示すとは、ユーザーさんにとっての良い意思決定ができる情報なのかを示すことです。
なぜ信頼を示さないといけないのか。
例えば、あなたが「ブログで副業をするための本」を買おうと思った時、
- 口コミが0件の本
- 口コミが100件がついた本
どちらの本を買いたいと思いますか?このような質問をしたら、かなりの高い確率で口コミが100件ついた本を選ぶかなと思います。
これは、あなたが失敗したくない、お金を無駄にしたくないと思い、良い意思決定ができるように、口コミが多くついている方を信頼し、安心して選んだ結果。
情報はあくまで情報でしかなく、何も保証がされていない状態です。
つまり、信頼とは保証(安心)であり、選びたいと思わせる期待でもある。
信頼を示す文章によって、文章のうまさを最大限引き出すこともできます。
信頼の根拠を示すための方法とは?
信頼の根拠を示すためには、
- 情報に対して理解度の深さを示す
- 信頼できる情報を補足する
大きく分けてこの2つがあります。
情報に対して理解度の深さを示す
理解度の深さとは、どれだけその情報に対して、深い専門的な知識を持っているか。
例えば「ブログ 書き方」で検索してユーザーさんが見にきてくれた場合、
あなた(書き手):ブログの書き方についてレベル7の理解度
ユーザーさん :ブログの書き方についてレベル1の理解度
この場合であれば、ユーザーさんが知らないことが、あなたのブログでたくさん書いてあるので、専門家としての信頼性を感じてもらえます。
しかし、
あなた(書き手):ブログの書き方についてレベル3の理解度
ユーザーさん :ブログの書き方についてレベル5の理解度
こんな状況で書かれた記事があれば、ユーザーさんの方が詳しい知識を持っていることになるので、あなたが書いたブログを見てもらっても、新たに得られる情報は少なく、信頼感は感じてもらえません。
理解度が深ければ、それだけ様々な情報を文章として出せるので、ユーザーさんが知らない情報を多数掲載できます。
自分が知らない情報がたくさんあると、専門性を感じるだけでなく、自分よりも多くの情報を持っているということで、信頼性(期待)も感じてもらえる。
そのため、文章を書くならば、その事に対してどれだけ深い情報を知っているかが重要になってきます。
信頼できる情報を補足する
深い情報理解だけではなく、他の方法でも信頼を感じてもらえる方法があります。
他人の信頼を付与させる
世間一般的に信頼を感じられる存在を出す
例:Googleが公表している~、弁護士の〇〇さんが~など
信頼を具体的にする
信頼を示せるよう具体的に表現する
例:2020年度は~、先月よりも120%アップ~など
引用や参考情報を入れる
公的機関などのデータを根拠として提示する
例:政府統計の総合窓口(e-Stat)、総務省統計局など
文章だけだと、どうしても具合性にかけるので、名前や数字やデータの引用先など、これらの根拠が感じられる情報を文章にも入れ込んでいきます。
自分の情報だけでは信頼性が出せない場合、他の要素をうまく活用して出すことも視野に入れておきましょう。
書き手の存在を示す
書き手の存在を示すとは、書かれた文章に人格を持たせるのと、誰がその文章を書いたのか存在をユーザーさんに示すことです。
文章は、書き手の中から生まれてきた言葉で作られているので、書き手の意識や考えていること、またはその時の感情によっても出てくる言葉が違ってきます。
ネガティブな気分なら、ネガティブ寄りの言葉が。
ポジティブな気分なら、ポジティブ寄りの言葉が。
このように、文章を書いていくと、だんだんとあなた自身が文章に乗り移っていきますが、さらに自分自身を反映できるよう意識していくことが必要です。
なぜこのような事をしないといけないのか。
それは、インターネット上にはたくさんの情報が集まっており、毎日何千何万何億のページが増えている状況。
当然その中には、同じような情報がわんさか存在しています。
そんな大量の情報の中に、他と似ているブログを書いたとしても、見向きもされません。
見てもらえない、気づいてもらえない、こんな状態は存在しないのと同じになります。
例えば、Aさん・Bさん・Cさんが同じように「ブログの作り方」について書いた場合、何か特別な特徴がないかぎり、同じように見えてしまって、選ぶのが大変ですよね。
しかし、他ブロガーさんとテーマが被ったとしても、あなたの存在が色濃く反映されているブログであれば、あなたのブログが選ばれる可能性は高くなる。
各文章やテーマは、どうしても似てきてしまうので、何が書かれているかではなく、誰が書いたのかが重要になります。
書き手の存在を示すための方法とは?
あまり特別なことをする必要はなく、
- 自分の考えや意見を入れる
- 人物像をイメージしやすい特徴を入れる
これをするだけでも大きく、ユーザーさんが感じる印象が変わってくるので、それぞれ詳しく見ていきたいと思います。
自分の考えや意見を入れる
文章に自分の考えや意見を入れるのは、批判をうけたり、間違ってしまわないか不安ですよね。
しかし、あなたが持つ独自の視点や解釈は、ユーザーさんの心を引き付けます。
取り入れるコツとしては、
- 自分はこうだと思ってる
- こうだと考えている
このような意見を、文章の中で入れていくだけなので、例文を下記に書いてみます。
「私はブログを書くときに、ユーザーさんを最優先した意識が大切だと思っています。」
どうでしょう…かなり簡単じゃないですか?
文章を書いている内に、このような書き方をしていることがあると思いますが、それを意識的に発動させながら「私はこう考えてる」という意見を、どんどん入れていきましょう。
ただし、書きたいブログのテーマについて、深く理解した情報がなければ、なかなか自分らしい意見が言えないことも多いので、最初に行ってもらう「情報への理解」が大切なんです。
人物像をイメージしやすい特徴を入れる
あなた自身の存在を、もっと出していくためには、ユーザーさんにあなたがどんな人物か、少しずつ文章の中で紹介していくのがオススメです。
口調
例:~なのです、~だ、など
心の声を出す
例:~になります(実は私もなんです)、~になる(こまっちゃいますよね)など
決まり文句
例:~して頂けると嬉しいです、さぁいってみましょう!など
プライベートの小出し
例:一緒に暮らしている猫ちゃんがいまして、2才になる息子がいて、など
他にもあると思いますが、さまざまな方法であなた自身のことをユーザーさんに知ってもらう情報を入れていく。
単なる文章が、情報が、いつの間にか「〇〇さんが書いているブログだ」という認識に変わり、どんどんあなたのブログを好きになってもらえる。
好きになってもらえると、文章もうまいと感じてもらいやすくなり、さらに読んでもらえる可能性が高まっていきます。
人物像がイメージしやすい特徴を、細かく入れ込んでいくことは、効果ありなんです!
文章が「へた」だと感じてしまう原因は?
私自身、たーーーくさん感じていますが、なんで自分の文章はこんなにも「へた」なのか…。
この問題はかなり根深いと思っています。…はい。
そもそも、なぜ文章が「へた」と感じてしまうのか。
今までの私の説明だとユーザーさんの「伝わった」が作れなく、書き手側の「伝えた」で止まっているからだと言えそうですが、もう少し深掘りしてみたいと思います。
今でもなんですが、特に私は文章の書き初め、初心者だったころによく「へた」さを感じていました。
長文を書く経験が少ない
→ 経験が少ないと感じ勝手に苦手意識が発芽
→ 苦手意識が無くならないまま負のスパイラル
→ 普段からやってないことは出来ないんだと諦め
こんな事態に陥っていたと思います。
他にも、
- 書いた記事のアクセスが増えない
- いくら書いてもアクセスが伸びない
- いつも指摘されたり怒られる
- 周りにうまいと思う文章を書く人がたくさんいて萎縮してしまう
別に上も下もないですが、勝手に自分の方が地位が低いと感じてしまっていました。
文章を書くのって、国語が出来る人、人気ブロガーさん、IQ200以上の天才じゃないと書けないんじゃないかなとまで思っていたんです。
しかし、周りのうまい文章を書く人たちも、私が使っている文字や単語を使っていることに気づいてからは、変な劣等感を抱かなくなりました。
周りを意識してるのは、まだ集中しきれておらず、向き合うべきユーザーさんに振り切れない。
そういった意識を強めて書いている内に、うまい文章は自分で判断するのではなく、全てユーザーさんが判断するもんだと思い、気にせず今も文章を書けています。
すみません…とくに明確な答えが出ているわけではないのですが、文章の「へた」さを無くすためには、文章を読んでもらいたい側と読みたい側のマッチング度を高めれば、自然と気にしなくなると思います。
文章の「うまい」は、相手がいて初めて「うまい」と思ってもらえる。
つまり、両想いになるように頑張ればいいってことですね。
文章がうまくなるためにやらなくていいこと
文章がうまくなるために、これだけはやらなくていいことをまとめてみました。
- 自分の文章に酔いしれる
- 難解な言葉を入れる
- 英語だらけ
- 私知ってるぜ感を出す(マウンティング)
書き手からしたら、ちょっとカッコイイ感じで文章を書きたい気持ちは分かります(私がそうなので…)。
しかし、ユーザーさんにしてみたら、一つも欲しくないものなので、文章が「うまい」と思ってもらえるように、やらなくていいことは、積極的にやらない方がオススメです。
最後に。
文章がうまくなるには、自分自身がどう感じるよりも、読み手であるユーザーさんがどう思うかが大切です。
書き手止まりの「伝えた」文章にするのか、読み手がしっかりと情報が受け取れる「伝わった」文章にするのか。
この意識だけでも大きく変わるので、あなたに少しでも「伝わった」」文章を書くための情報として、この記事が役立てられれば嬉しいです。著者:osugi(@osuuuugi)